はじめに
「子どもの考えていることが分からず、どう接していいか分からない」「自分の子育ては本当に正しいのだろうか…?」仕事と育児の両立を頑張る私たちは、日々そんな不安と向き合っていますよね。
僕自身も、日々子育てに悩みながら試行錯誤する中で、とある一冊の本に出会いました。それが『児童精神科医が「子育てが不安なお母さん」に伝えたい子どもが本当に思っていること』です。
タイトルは「お母さん向け」ですが、子どもの気持ちを理解する上で、親としての立場は父親も母親も同じ。むしろ、私たち共働きパパにとっても目から鱗の学びが詰まっていました。特に僕は社会福祉士の資格も持っているので、この本の中で述べられていることは非常に適切であると感じました。
この記事では、この本から得た仕事と育児を両立する父親に役立つ3つのポイントを厳選してご紹介します。この記事を読めば、子どもの気持ちが分かり、育児への不安が和らぎ、心に余裕が生まれますよ。
仕事と育児を両立する父親に役立つ3つのポイント
お父さんだって完璧じゃなくていい
「子どものお手本になるために、絶対に失敗してはいけない」──そう自分にプレッシャーをかけていませんか?
この本を読んでハッとしたのは、「完璧な親」を目指す必要はないということです。親も一人の人間。育児や仕事で失敗したり、間違えたりする姿を素直に認めることも、子どもにとっては立派なお手本になります。
大切なのは、失敗からどう立ち直り、前に進むか。その姿を見せることで、子どもは「失敗しても大丈夫なんだ」と学び、自己肯定感を育むことができます。頑張りすぎて不安を抱え込んでしまうパパこそ、「完璧じゃなくていい」と肩の力を抜いてみませんか?
夫婦げんかで子どもを不安にさせない工夫
仕事でクタクタになって家に帰ると、些細なことでイライラしてしまい、奥さんと口論になってしまうことはありませんか?
この本には、「親の怒りや大きな声は、子どもをとても不安にさせる」と書かれています。たとえ子どもに直接怒っていなくても、エスカレートした夫婦げんかは子どもにとって辛い経験となり、情緒不安定につながることもあるそうです。
ではどうすればいいか?ポイントは2つあります。
- 「おだやかに話す」を意識する: 疲れているときこそ、小さく・ゆっくり・おだやかなトーンで話すことを心がけてみましょう。不思議と自分の気持ちも落ち着いてくるはずです。
- 仲直りの姿を見せる: もし喧嘩をしてしまっても、きちんと「仲直りする姿」を子どもに見せてあげることが重要です。「ごめんね」と謝り、許し合う姿は、子どもが社会性やコミュニケーション能力を学ぶ上で大切な機会となります。
一人で抱え込まず、頼る力を持つ
育児も仕事も「自分が頑張らなければ」と、すべてを一人で抱え込んでいませんか? この本で最も心に刺さったのは、「つらい時には、誰かを頼っていい」というメッセージでした。奥さんと正直に気持ちを共有し、「今日は疲れているから代わってほしい。その代わり明日は僕がやるよ」と助けを求めることも、立派なチーム育児です。
さらに、家庭の外に目を向けることも大切。地域の子育て支援サービスは、パパが思っている以上に充実しています。保育園や幼稚園だけでなく、無料で利用できる児童館や子育てサロン、養育相談など、利用できる場所はたくさんあります。 限界を迎える前に「助けて!」と言えることで、心にゆとりを生み、結果として子どもに安心感を与え、家族みんなの幸福度を高めることにつながります。
まとめ
今回は、共働きパパの育児の悩みに応えてくれる『児童精神科医が「子育てが不安なお母さん」に伝えたい子どもが本当に思っていること』から、「完璧じゃなくてもいい」「夫婦で協力する」「人に頼る」という3つの大切なポイントをご紹介しました。
完璧な父親を目指すのではなく、等身大の自分で向き合うこと。そして、奥さんや外部の支援にも頼ることで、心にゆとりが生まれるはずです。 日々の育児は大変ですが、僕たち共働きパパの努力は必ず子どもに伝わります。この本が、あなたの育児と仕事の両立を少しでも楽にする手助けになれば幸いです。一緒に楽しみながら、子育てを頑張っていきましょう!

児童精神科医が「子育てが不安なお母さん」に伝えたい 子どもが本当に思っていること [ 精神科医さわ ]
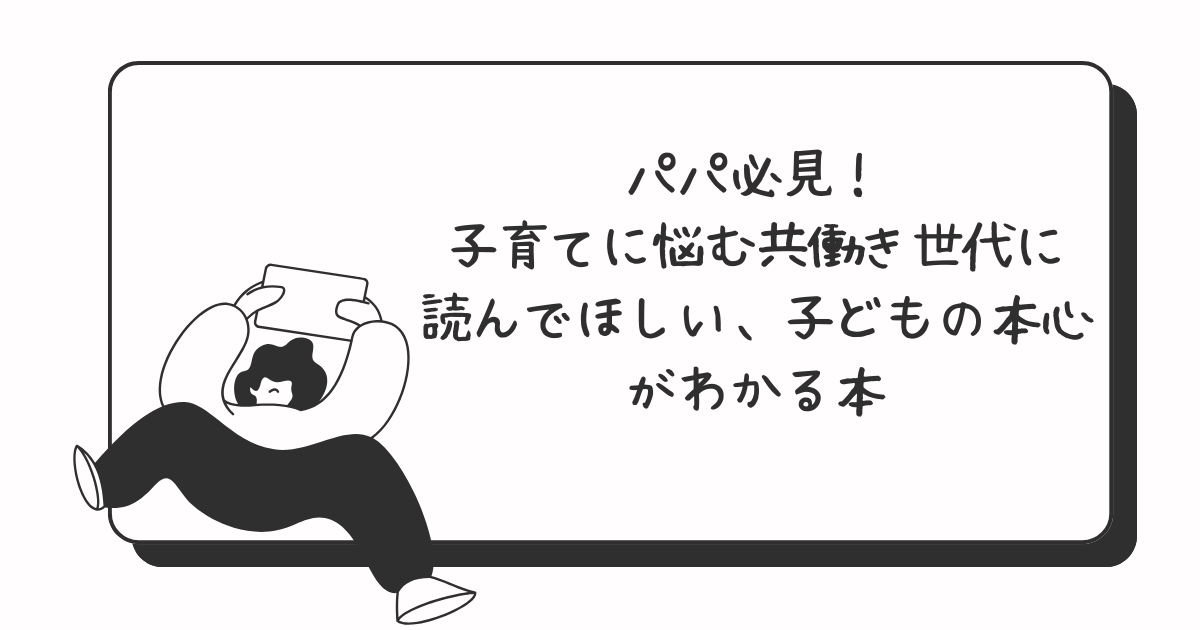
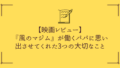
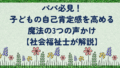
コメント